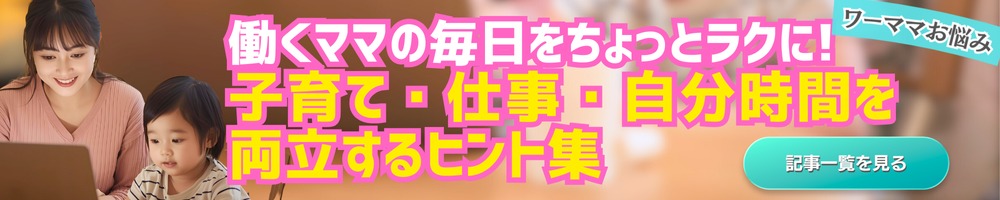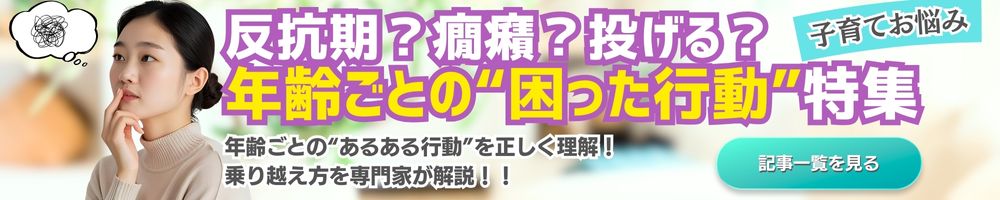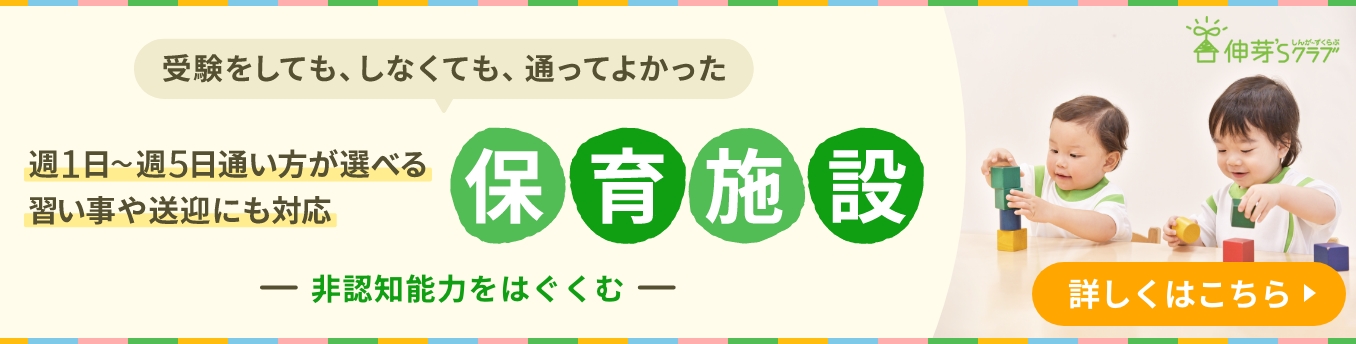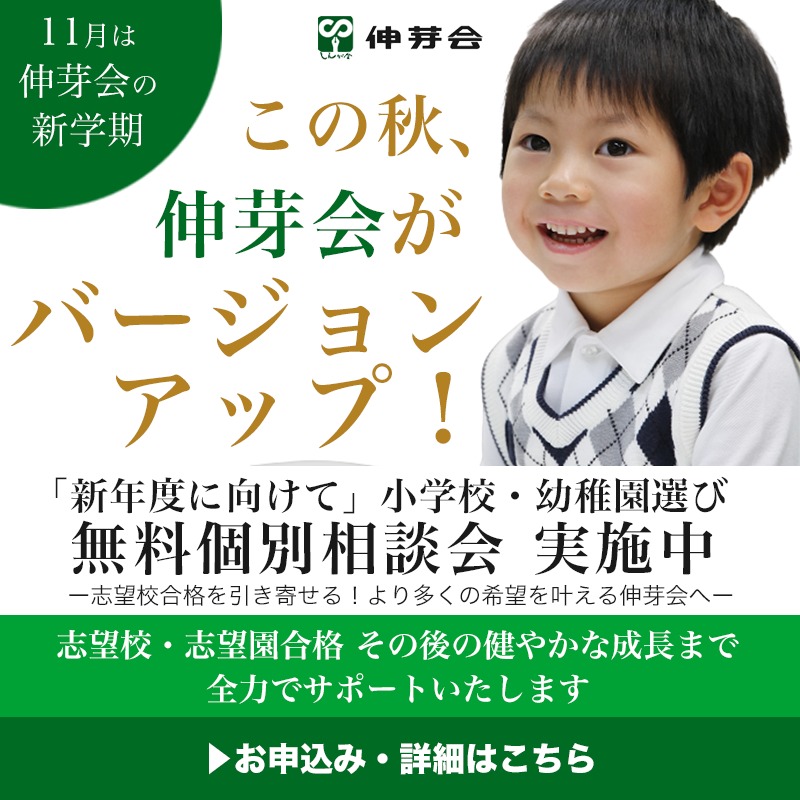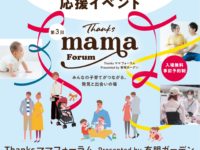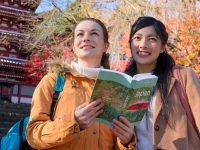きょうだい喧嘩を親のストレスなく止める方法7選【公認心理師監修】

きょうだい喧嘩は、小学生あたりまでの子育てでよく見られる光景ですが、毎日繰り返されると親のストレスにもなりがちです。「もっと上手に対応できれば」と悩む人も多いのではないでしょうか。
この記事では、きょうだい喧嘩を「イライラの火種」から「子どもの成長を促す関わりのチャンス」へと変えるための方法を公認心理師の佐藤めぐみさんが解説します。
ステップ1 きょうだい喧嘩に対する見方を変える

きょうだい喧嘩に悩むご家庭にとって、「喧嘩=悪」に映りがちですが、その視点を変えることから始めましょう。子どもたちはきょうだい喧嘩を通して、
・自分の思い通りにならない場面があるということを知る
・自分の意思をはっきりと主張する機会を得る
・悔しい、悲しい、ムカつくといったネガティブな感情に直面し、どう向き合うかを学ぶ
・相手に譲る、折り合いをつけることを少しずつ学ぶ
など、さまざまな経験をしています。これらを読むと、
「確かに社会経験ではある」
「お友だちとの人間関係で“ぶっつけ本番”より、きょうだい間で場を積んでおいた方がいいかもしれない」
と思える方もいるのではないでしょうか。
きょうだい喧嘩を「人間関係の練習」と捉えることで、喧嘩の見え方も変わってくるはずです。
・きょうだい育児に関する親子の関わり方については、こちらの記事をご覧ください。
『きょうだい差別は愛情格差なの? 子どもに与える影響と親の対策』
ステップ2 “交通整理役”になる
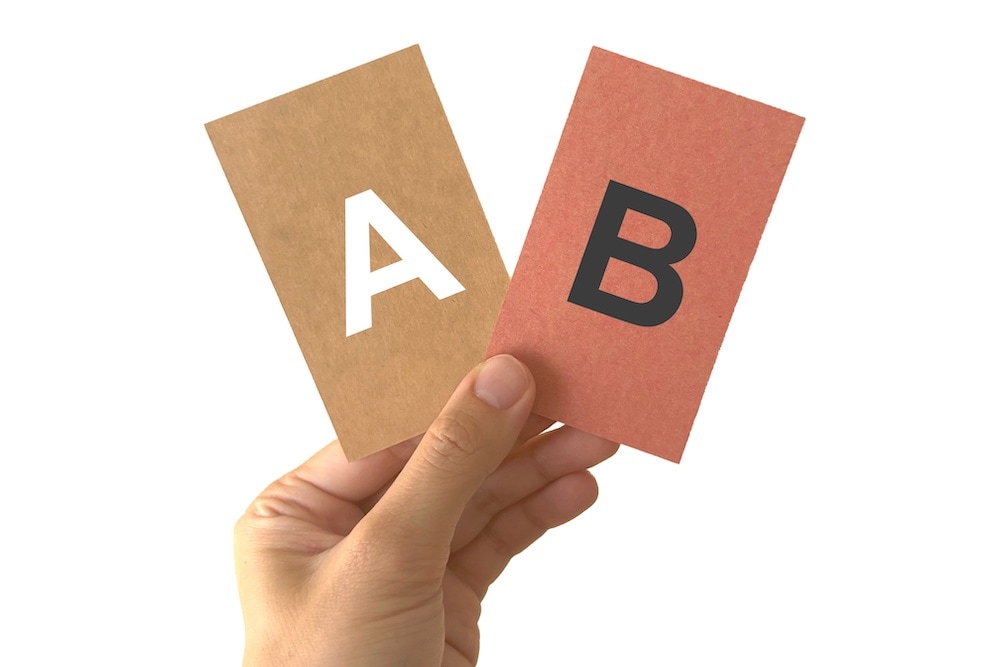
きょうだい喧嘩が始まると、親はつい「誰が先にやったの!?」と犯人探しの“審査官”になってしまいます。
しかし、この問いかけは親のイライラを増大させるだけでなく、子どもにとっても「自分は悪くない」と主張し合うだけの不毛な時間になりかねません。
“審査官”から“交通整理役”になれると、親も感情のヒートアップが抑えやすくなります。
たとえば、
・何が起きているかを整理する
「お兄ちゃんはおもちゃを貸したくないと思っているんだね」
「妹ちゃんはそのおもちゃで遊びたかったのね」
など、それぞれの気持ちや状況を整理して伝える
・子どもたちに考えさせる
気持ちや状況を整理したら、それを踏まえて「どうしたらいいか」を子どもたちに考えてもらう。親が「こうしなさい」と一方的に指示すると反発されがちなので、
「2人で遊ぶにはどうしたらいい?」
「他にどんな方法がある?」
など考える機会を持たせる
・選択肢を提示する
子どもたちが解決策を思いつくことができない場合は、
「順番に使う」
「一緒に遊ぶ」
「他のおもちゃを探す」
など、具体的な選択肢を提示していく
子育てでよくあるのが、親が自らの言動で自らの感情を逆なでしてしまうこと。
“審査役”の「誰がやったの!?」はその典型です。“交通整理役”という感情を入れ込まないアプローチをすることは、親のイライラ防止につながるので結果的に「自分(親)のため」でもあるのです。
これまで親が大声で制止するやり方をしていた場合、喧嘩の最中にこんな冷静なアプローチなんて「ムリ!」と思うかもしれませんが、問題解決に向けた姿勢を親自ら示せると、それ自体が子どもの学びになります。
試行錯誤しながらでいいので取り入れてみてください。
・きょうだい喧嘩が起きる子どもたちの心理やおすすめの対処法については、こちらの記事もご覧ください。
『おうち時間で増える、兄弟喧嘩の正しい対処法とは?』
ステップ3 叱るより“実況中継”してみる
感情的になって声を荒げてしまいそうな時は、怒るよりも“実況する”ことで、親自身も落ち着きを保ちやすくなります。
たとえば、
「弟くんはお兄ちゃんの持っているおもちゃが欲しい」
「2人でおもちゃの引っ張り合いをしている」
「お兄ちゃんが大きな声を出している」
「弟くんがママのところに駆け込んできた」
という感じです。スポーツの実況中継のように目の前で起きていることを淡々と言葉にする行為は、事実を述べるだけに留める分、評価や感情的な解釈が入り込みにくくなります。
それにより親が気持ちを抑えやすくなるのです。また、子どもたちにとっても自分たちの振る舞いが耳から入ってくることで、一歩引いて客観的に状況を見つめ直すきっかけにもなります。
ステップ4 親の気持ちを伝える

親も感情を持った1人の人間です。きょうだい喧嘩で困った時は、その気持ちを素直に伝えるのは悪いことではありません。ただ伝え方にポイントがあります。
【NG例】
「あなたたちの声がうるさ過ぎて頭が割れそう!」(子どもたちを責めている)
↓
【OK例】
「2人が喧嘩しているとママは悲しい気持ちになるな」(親が自分の気持ちを吐露している)
このように、「あなたたちが悪い」ではなく「私はこう感じている」という表現を使います。俗に言う「I(アイ)メッセージ」です。
自分が責められているニュアンスが消えるため、子ども側も耳を傾けやすくなります。
親が自分の気持ちを表現することで、子どもたちが「自分の行動が、他の人に影響を与えている」と気づいてくれれば、喧嘩のあり方を見直す機会にもなるでしょう。
ステップ5 「今は距離をとろう」で一時中断する
喧嘩がヒートアップして、お互いに手が出そうになったり、聞く耳を持たなくなったりしたとき、その場で「はい仲直り」なんてとてもできません。
そんなときは時間と距離が助けになることが多いです。喧嘩でイライラしている子も泣いている子も、時間が経てば落ち着いてきます。さらに現場から離れることで気持ちが切り替えやすくなります。
「今は2人とも気持ちが熱くなっているから少し時間を置こう」
「2人ともここから一度離れて自分のお部屋で過ごそう」
「10分したらまた一緒に遊べるか考えてみよう」
激しい喧嘩をその場で収束させようとすると、親もつい大声を張り上げることになり、さらに大ごとになってしまうことさえあります。
距離を作り、時間を置く。この2つは気持ちを落ち着かせる効果が高いので、焦って飛び込まないようにしましょう。
ステップ6 子どもに解決の主導権を返す

子どもたちが喧嘩を始めると、「自分が止めなければ!」というスイッチが自動的に入ってしまう人も多いのですが、親がすべての問題を解決してあげる必要はありません。
いずれ子どもたちも自ら問題を解決する能力を身につける必要があるので、解決の主導権を子どもに持たせる経験も大事です。まずは軽いもめごとのときに、
「今回ママは見守っているから2人で話し合って決めてごらん」
「どうやったら仲良く遊べるか一緒に考えてみようね」
「困ったら呼んでね」
のように、声をかけてみてはいかがでしょうか。最初は上手くいかなくても「仕方ない」とし、その中での「よかったこと」を意識的に見つけてほめてあげると理想的です。
「いつもより気持ちを抑えられたね」
「泣かなくてえらかったね」
と具体的に望ましい行動を言語化してもらうことで、子どもたちにも「これでいいんだ」ということが伝わりやすくなります。
ステップ7 終わったあとに振り返る

きょうだい喧嘩が収まり、お互いが落ち着いたタイミングで、一緒に振り返る時間を持つのもおすすめです。
「次に同じことが起きたら何ができそう?」
「今度はどんな風に遊んだら楽しいかな?」
ここでのポイントは2つあり、過ぎたことの深掘りをしないこと、お説教をしないことです。あくまでも、子どもが自分の気持ちを整理し、次への学びにつなげるためのサポートです。
2~3歳の子どもにはまだ難しいと思いますし、子どもが話したくないようなら無理に聞く必要はありませんが、この短いふり返りタイムで、子どもの中に「次はこうしてみよう」という前向きな気持ちが生まれれば大きな収穫です。
・親が、下の子と比べて上の子をかわいいと思えない理由や対応については、こちらの記事をご覧ください。
『【公認心理師監修】「上の子かわいくない症候群」とは? 要因や対応策について解説』
親が落ち着いて対応できれば親子どちらにもメリットあり
きょうだい喧嘩への対応は親にとって大きなストレスになりがちですが、感情的になって大きな声で仲裁に入ると、かえって喧嘩がエスカレートしてしまうことも少なくありません。
親が落ち着いて対応できれば、子どもたちにも望ましい姿勢を示すことになるので親子両方にメリットがあります。
ぜひ今回お伝えした方法の中から1つでもいいので今までと違う方法できょうだい喧嘩のアプローチのヒントにしてみてください。

きょうだい差別は愛情格差なの? 子どもに与える影響と親の対策

相談の場「育児相談室ポジカフェ」&学びの場「ポジ育ラボ」を運営。
専門は0~10歳のお子さんを持つご家庭向けの行動改善プログラム、認知行動療法ベースの育児ストレス支援。ポジ育ラボでは子育てに関する心理学情報を発信するほか、ママ・パパが自分の心のケアを学べるメルマガ講座「ポジ育クラブ」を配信。英・レスター大学大学院修士課程修了。HP:https://megumi-sato.com/