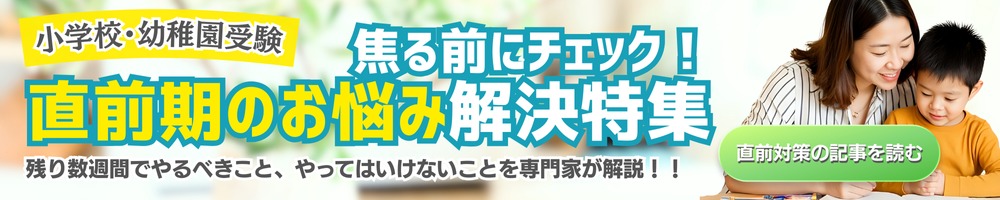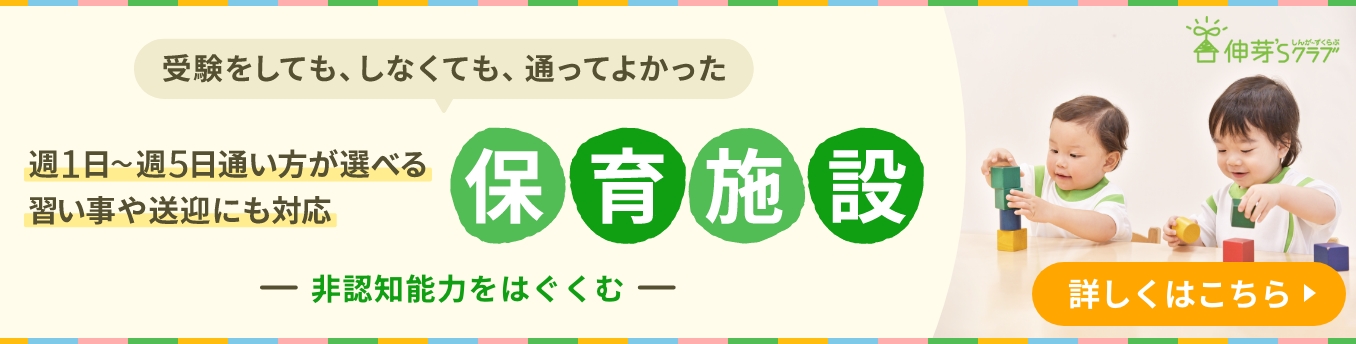【年齢別お手伝い&効果】子どもの生活力を高めるオーストラリアの家庭教育

オーストラリアでは、家庭でのお手伝いが子どもの生活力を育てる大切な役割を担っています。お小遣いも「仕事の対価」として考えられ、働くと報酬が得られるという仕組みを小さいときから学びます。家族全員で家事を分担する文化も根付いており、子どもも家庭の一員としての役割を果たします。本記事では、日本との教育観の違いを交えながら、年齢別のお手伝い事例などを紹介します。
お小遣いは「家事の報酬」が一般的
オーストラリアでは、日本のように毎月決まった金額のお小遣いを子どもに渡す家庭は多くありません。その代わりに、お手伝いの内容によって報酬を渡すスタイルが一般的です。
オーストラリアではお小遣いのことを“Pocket Money (ポケットマニー)”と呼び、文字通り「ポケットに入るくらいの少額」を意味しますが、金額は仕事によって決まります。例えば、「芝刈りは5ドル」「車の掃除は2ドル」というように、内容に応じた報酬を話し合いによって親子で決め、やり遂げたらお小遣いが支払われます。
また、一緒に暮らす家族は家事を分担するのが当然と考える家庭が多く、全員で家事を分け合って生活しています。たとえば、「料理はお父さん」「掃除はお母さん」「食後の片づけは長男」「洗濯物をたたむのは次男」といった具合に、家族それぞれが自分の役割を持ち、それを自分の仕事として責任を持って行うのが自然な形となっています。
年齢別・家庭でできるお手伝い事例
お手伝いの内容は、子どもの年齢や成長段階に応じて段階的に変わっていきます。以下は、オーストラリアの家庭で実際によく見られる年齢別のお手伝い事例と身に付く力です。
未就学児(2~5歳)
・おもちゃや本の片付け:使った物を元の場所に戻すことで「整理整頓」の基本を学びます。
・植物への水やり:日々の世話から「継続する力」や「命への関心」が育ちます。
小学校低学年(6〜8歳)
・テーブルセッティング:食事の準備を手伝うことで「思いやり」や「家族への貢献」を実感できます。
・洗濯物の仕分けやたたみ:細かな作業を通じて「観察力」や「丁寧さ」が育ちます。
小学校中高学年(9〜12歳)
・料理の手伝い(オーブン料理、パスタなど):「段取り」や「火の扱い方」、「安全意識」を学びます。
・掃除機がけやゴミ出し:定期的なタスクを通して「時間管理力」や「責任感」を育てます。
中高生(13歳以上)
・弟妹の世話や夕食作りを自ら申し出る:「自発性」や「計画性」を育てます。
・芝刈りやペンキ塗り:自分の行動が誰かの役に立つという「達成感」を学びます。

学校では家事体験ができないオーストラリア
オーストラリアには、日本の小学校にあるような家庭科や技術といった教科がありません。そのため、学校で料理や裁縫、物作りなどを習うことがほとんどないのです。また、掃除の時間も設けられておらず、校内の清掃は専門の清掃員が行います。従って、生徒が雑巾を絞ったり、ほうきやちりとりを使ったりする機会もありません。
このような背景から、オーストラリアの子どもは家庭でのお手伝いを通して料理、裁縫、掃除などを学びます。子どもの生活力を育てるためにも、お手伝いがとても重要だと考えている家庭が多いのです。実際にオーストラリアで暮らしてみると、日本の教育現場がいかに「生活力」や「時間管理力」「責任感」などを育てる仕組みになっていたかを改めて実感させられます。
我が家のお手伝い実践例と報酬
我が家では、高校2年生の娘は中学入学以降、「食後の食器の片づけ」と「朝の犬の散歩」を担当しています。たとえ試験期間や予定が詰まっている日であっても、自分の代わりに家族の誰かにお願いするなどの調整をしない限り、自分の役目として責任を持って実行します。「忙しいから」はできない理由にならないと伝えているのは、大人も忙しいなかで日々時間をやりくりして生活しているという現実を学んで欲しいからです。
また小学校5年生の息子には、「朝晩のカーテンの開け閉め」「食洗機から食器を出して棚に戻す」「洗濯が終わったら洗濯機から出す」といった日常的な役割があります。これらの子どもたちの仕事に”ポケットマニー“を渡す家庭もありますが、我が家は「家族で分担する家事の一部」という考え方のためお小遣いは渡していません。
お小遣いが欲しい時は、「車の掃除をするから3ドル欲しい」「50ドルの服が欲しいから今週は毎日夕食を作る」というように、自分から提案して報酬を交渉します。このように、自分で仕事を見つけて報酬を得るという流れが、社会に出た際の働き方にもつながっていくと思います。

まとめ
お手伝いは単なる作業ではなく、「自立への一歩」です。親がした方が早いと感じることもありますが、時間をかけて子どもに任せることで、生活に必要な知識や力が少しずつ身に付いていきます。
とくにオーストラリアのように学校で家事ノウハウを学ぶ機会が少ない環境では、家庭での経験が将来必要な「働く力」の土台となります。家庭の中での小さな役割が、子どもたちの未来を育てているのです。
<参考URL>
https://raisingchildren.net.au/preschoolers/family-life/routines-rituals-rules/chores-for-children
https://families.org.au/article/age-appropriate-chores/

オーストラリア式「叱らない育児」は子どもと対等に接する!

オーストラリアはエシカルスイーツで子どものエコ意識を育む【海外のおやつ】
世界35か国在住の250名以上の女性リサーチャー・ライターのネットワーク(2019年4月時点)。
企業の海外におけるマーケティング活動(市場調査やプロモーション)をサポートしている。