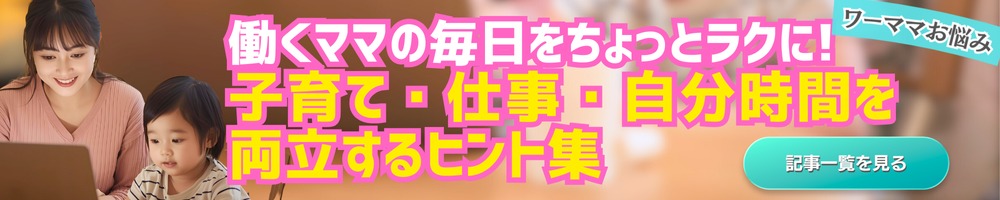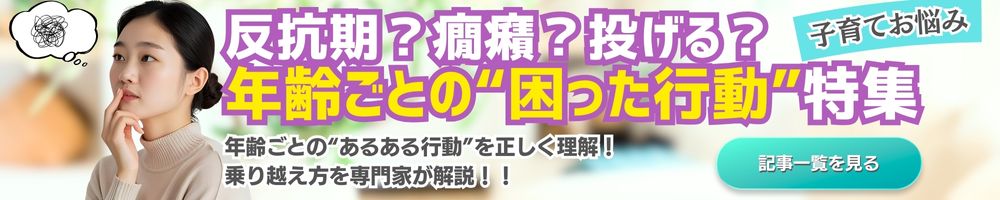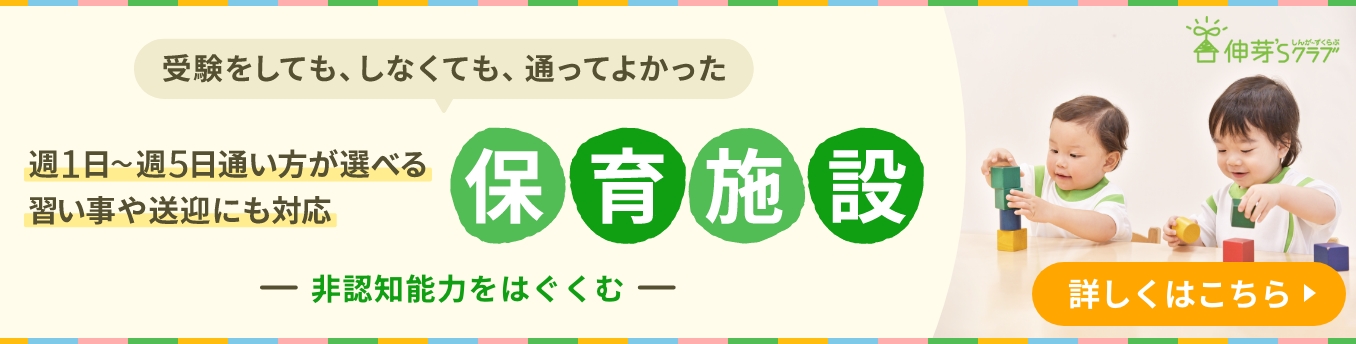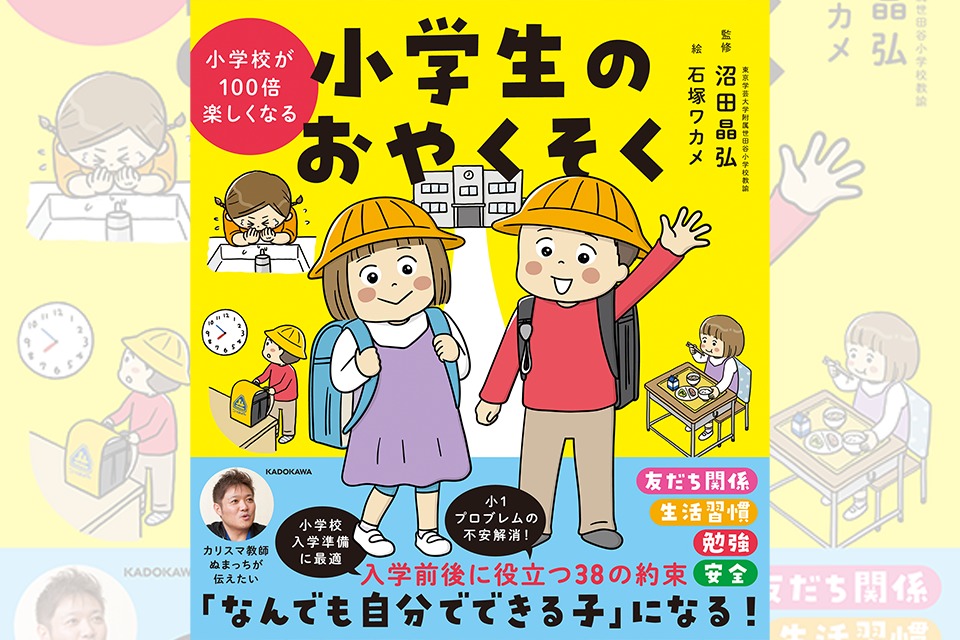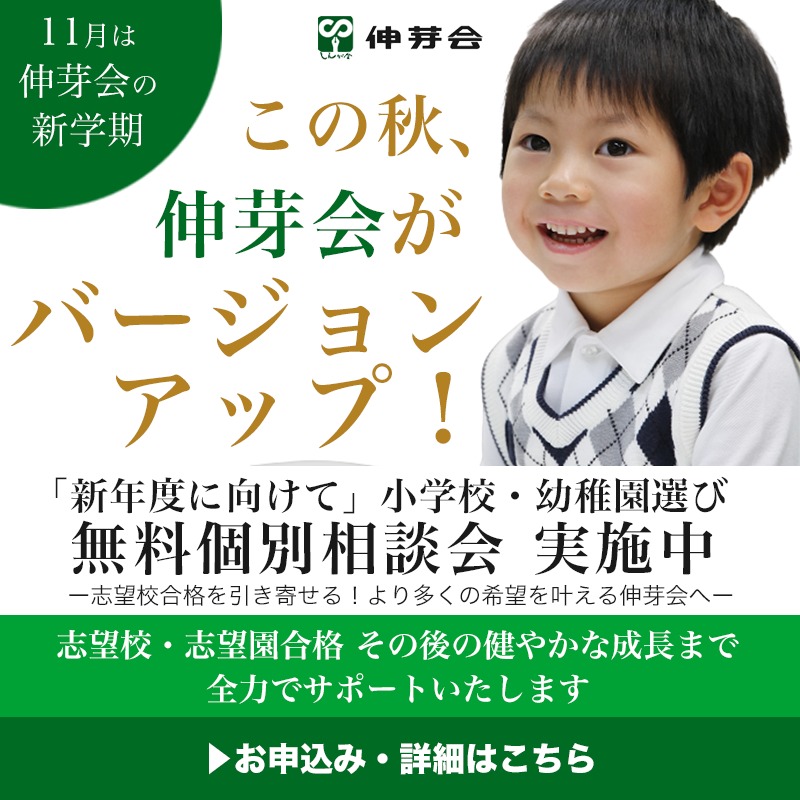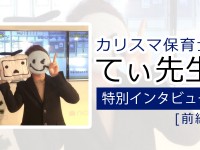学校でわが子が“お世話係”になったときの対処法

小学校では、先生からある特定の子に「お世話係」を依頼することがあります。その存在は学校によりけりですが、お願いされた場合、子どもやその親が悩むケースも少なくありません。
今回は、自分の子どもがお世話係になったときにどう対応していったらいいのかについて、事例を交えながら、親が意識すべきポイント、そして家庭での話し合いのコツについて公認心理師の佐藤めぐみさんが解説します。
「お世話係」の子が抱えやすい悩みとは

学校内での“お世話係”とは、一般的に学習面や行動面でそのクラスのペースについていけない子のサポートをする係のことを指すことが多いです。
ただ、黒板係や給食当番のような誰もが知る役割とは異なり、担任の先生に内々にお願いされる、いわば“表にはない係”。学校によって位置づけが異なりますが、中には特定の子に偏ってしまうこともあるため悩むケースも散見されます。
たとえば、
・クラスで落ち着きがない子の隣にされ、「○○さんは優しいからお世話をお願いね」と言われた
→その子の動向が気になり、授業に集中できない
・校外学習や遠足のときなどに、「一緒に行動してあげてね」「困ったら助けてあげてね」と先生に頼まれた
→自分の仲良しグループと楽しむことが十分にできなかった
・クラスの休みがちな子に対し、「ノートを見せてあげて」「聞かれたら教えてあげてね」と先生に頼まれた
→時間的にも精神的にも負担が大きくなり、自分が学校に行きたくなくなった
お世話係はしっかりした子が任される傾向があるため、同じ子が何年間も担っていることもあるようでSNSでも話題になりました。
クラス替えがあっても、席替えがあっても、セットで動いているとなれば、負担が大きくなるのは当然です。
・新学期のお悩みに関してはこちらの記事もご覧ください。
わが子が「お世話係」に任命されたら親が行動すべきこと
もし自分の子どもがお世話係を任されたら、親はどのように対応すればよいのでしょうか?
1.まずは本人の気持ちを確認する
お世話係の役割を引き受けることに対して、子ども自身がどう思っているのかをしっかり聞きましょう。
・「やりがいを感じている」 → 無理のない範囲で応援する
・「負担に感じている」「嫌だと思っている」 → 相談が必要
2.引き受けた場合はその後の経過もフォローしていく
「頼まれた」ということだけでなく、実際にやってみてどうなのか。
「想像していたより大変」
「だんだんとしんどくなってきた」
ということもあるでしょう。
こういう意思疎通が日頃からできているご家庭であれば、子どもが行き詰まり、親がそれに気づけないということはないかと思いますが、中には「いったん引き受けたけど、やっぱりやりたくない……」と言えずにそのまま継続してしまう子もいるので、「最近はどう?」とその後の様子もフォローしていきましょう。
3.辞退する場合も子どもだけに任せない
はじめから「やりたくない」と感じている場合や、引き受けたものの途中で負担に感じている場合、無理に続けさせる必要はありません。
お世話係は本来、特定の子どもが負担を背負うものではなく、学校全体で支援すべきことです。さらに言えば、お世話される側の子も、いつも1人の子と接するとなると、関わりやコミュニケーションが限定されてしまいます。
とくに、何年も続いている、あるいは負担が大きすぎると感じたら、迷わず学校に相談しましょう。
その際に、子ども自身が先生に直接言って話が通じればそれでいいですが、励まされるだけでそのまま継続というケースもあるようです。
子どもに完全に任せるのではなく、その後の様子を聞き、子どもだけでは対処が難しいようなら、親が先生に直接相談しましょう。
中には、「先生に意見するとうるさい親だと思われるのでは」さらには「モンスターペアレントに思われるのでは」と行動を迷ってしまう人もいるようですが、その子が負担に感じているのであれば、それを伝えるのは正当な権利です。
相談する際は感情的にならずに、
「子どもの様子を伝える」
「学校としてどのような対応ができるのかを聞く」
といった形で話すとスムーズでしょう。
家庭でも「お世話係」について話し合っておこう
先述の通り、お世話係は表立った係ではない分、実態が公になりにくい性質のものだと思います。
お世話係が存在するかしないかは学校によっても違いがあると思われますが、もし「うちの学校はあるらしい」という場合は、先生に言われてから考えるのではなく、あらかじめ家庭内で「お世話係の存在」を話し合う機会を持てるといいでしょう。
その方が、ある日急に舞い込んできたときに慌てずに対応できるはずです。
話し合うポイントとしては、以下のようなことが挙げられるかと思います。
・お世話係というものがあること
・そこではどんなことを期待されているのかということ
・負担を感じたら無理せずに先生や親に相談すること
今回の記事では、お世話係を任されて困っているときの対応について書いているので、なんとなく「お世話係」を悪いイメージだと決めつけているように思えるかもしれません。ですが、任された子が実際に快くサポートできれば、その子にとってとても実りある経験になるはずです。
助けが必要な子を支える経験ができていることは、何よりその子の自信になりますし、優しさ、気配り、困っている側の視点を知るなど、非認知能力の向上につながります。本人が楽しめているならメリットも多いということです。
・非認知能力に関する記事はこちらをご覧ください。
ただ、お世話係の特性上、「いい子」「しっかりしている子」が任されやすく、そのようなタイプの子は大人が期待する「いい子」でありたいと思う子も多いものです。
・“いい子気質”に関する記事はこちらをご覧ください。

チェックシート付き!「いい子」だってストレスを抱えている!?
大人がその思いを利用するのは避けるべきで、家庭内で話す場合もニュートラルな立ち位置で話題に出すことがポイントだと思っています。
つまり、お世話係について、よくも悪くもイメージを植えつけないということです。それは子どもが判断することであって、大人が評価を加えてしまうと、子どもが持つイメージを歪曲してしまいかねません。いつか声がかかった場合の事前知識という形で伝えられると望ましいでしょう。
現役小学校教師がクラス運営について意識していること
「お世話係」について、東京学芸大学附属大泉小学校の現役教師でありながら、これまでの教育概念に縛られない自由な発想で子どものやる気と自主性を伸ばす教育で注目を集める“ぬまっち”こと沼田晶弘先生(@numatch16)にご意見を伺いました。
__先生は「お世話係」を任命したことはありますか?
ボク自身はこれまで誰かに特定の子のお世話を任命したことはありませんが、ボクを助けてくれるお世話係はクラスにたくさんいます(笑)。
たとえば「今日避難訓練があること」などを忘れがちなのですが、子どもたちの方が学校通信をよく読み込んでくれているので、朝登校すると「先生、今日は避難訓練だよ」と教えてくれます。
他にも、アレルギーがある子はご両親の許可を得てクラスで情報を共有しておくと(もちろんボクも確認しますが)、クラス全体で間違いがないかをチェックする体制になっています。
子どもって本来誰かをお世話することが大好きだし、学びの機会にもなるはずです。ただ、それがルール化されて強制されると話は変わってくるので、本人や周囲に「やらされている感」「イヤイヤな空気」がないことがポイントなのではないでしょうか。
__席替えに関して意識していることはありますか?
クラス運営を任されている担任としては、何かしら理由があって席を決めることもありますが、ボクの専科授業では自由席にしています。
「同じ子と連続して隣にならないこと」などのルールを設けると、子どもたちが考えて座りますし、たとえ気に入らない席になったとしても次の授業ではまた変わるので特に不満も出ません。
むしろ、いい席に座りたいから遅刻も減りますし、いつも近くに座る子が離れていたら「何かあったかな?」と変化に気づくこともできます。
__「お世話係」に関して親御さんにメッセージをお願いします
結果的に同じことをやるとしても、指令の受け取り方や先生との信頼関係によってだいぶ捉え方が異なってくるので判断が難しいですよね。
一つの目安として、もし同じ子と3回連続で同じ席になって、それに対してお子さんが嫌だなと思っているようであれば、「別の子とも関わらせたいのですが、何か理由があるのでしょうか?」と先生に聞いてみてもよいと思います。
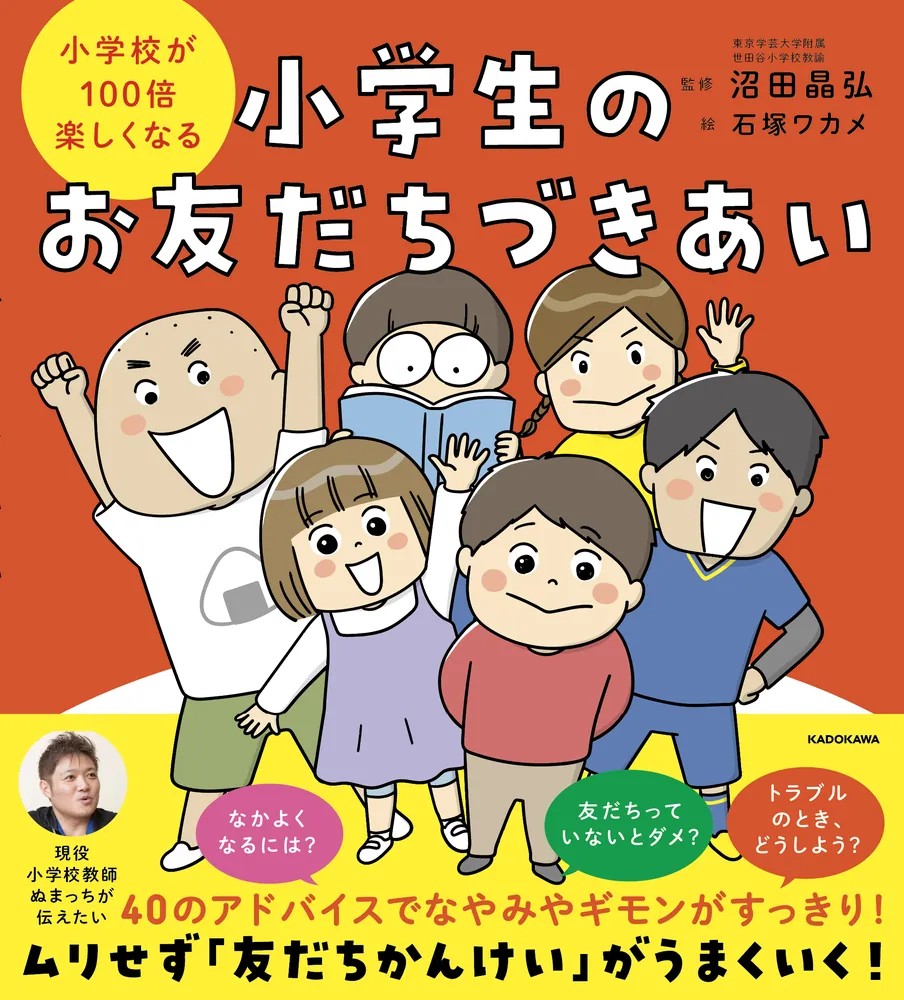
ぬまっち先生の最新著書『小学校が100倍楽しくなる 小学生のお友だちづきあい』(KADOKAWA)が現在発売中!
・沼田先生から小学生の親御さんに向けたアドバイスは、こちらの記事もご覧ください。
学校と連携しながら状況に応じた判断を
お世話係は表立った役割ではない分、実態が見えにくいですが、困っている人を助けるということ自体はその子のその後にも活きる経験になりえます。一方で、子どもが「嫌だ」と感じているのに無理に続けさせてしまうと、その子自身の学校生活に影響が出る可能性もあります。
いくらしっかりした子であっても、お世話係が合う子、合わない子はいると思いますし、お世話される子との相性もあるはずです。お世話係全体をひとくくりに否定したり肯定したりするのではなく、その子自身が1つ1つのケースを主体的に選べる環境を整えることが無理のない助け合いにつながると思うので、学校と連携しながら無理なく過ごせるようにしていきましょう。

いじめ、不登校、小4の壁…新入学&新学期につまずかない4つのコツ

うちの子がお友だちを叩いた!親としてどうすべき?

相談の場「育児相談室ポジカフェ」&学びの場「ポジ育ラボ」を運営。
専門は0~10歳のお子さんを持つご家庭向けの行動改善プログラム、認知行動療法ベースの育児ストレス支援。ポジ育ラボでは子育てに関する心理学情報を発信するほか、ママ・パパが自分の心のケアを学べるメルマガ講座「ポジ育クラブ」を配信。英・レスター大学大学院修士課程修了。HP:https://megumi-sato.com/