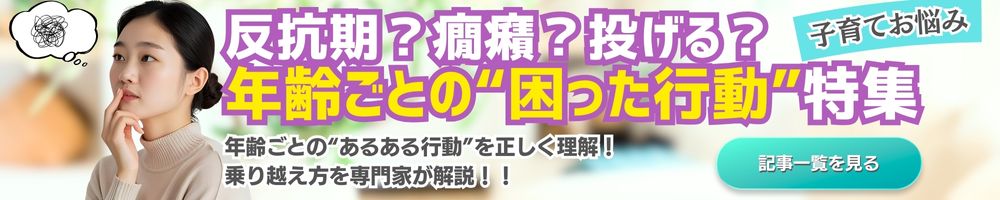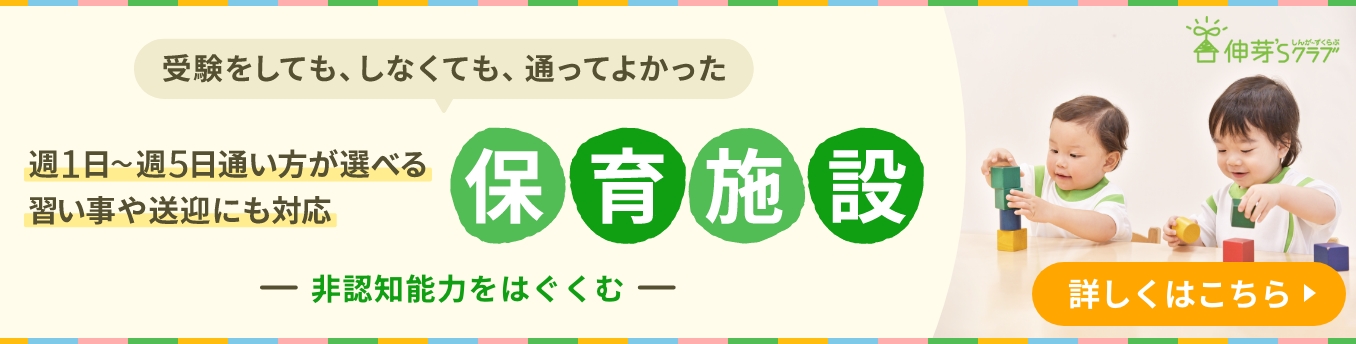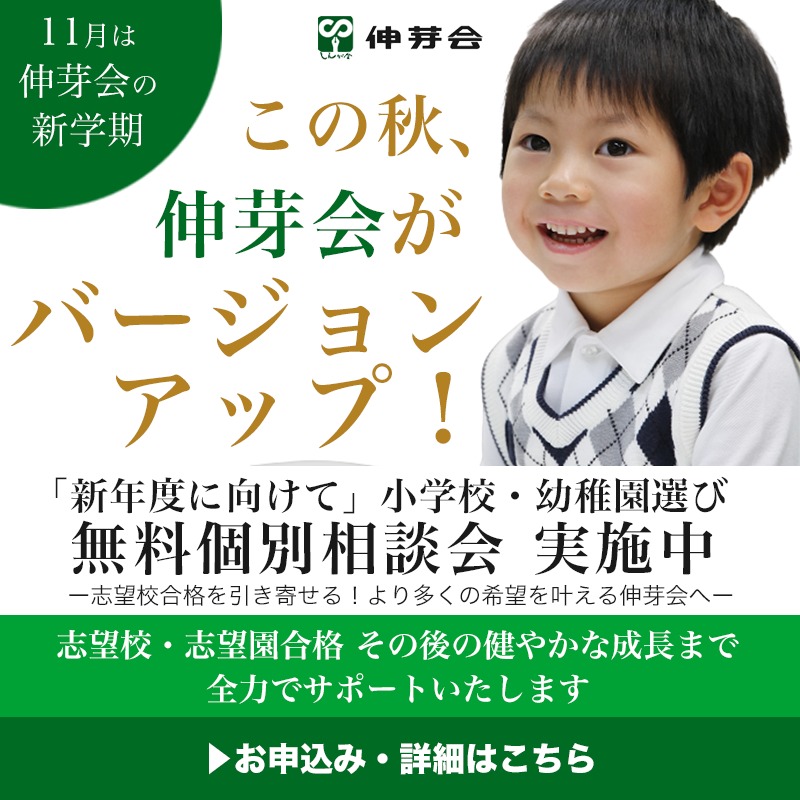子どもが“友だちのおもちゃを取った”ときの年齢別の理由と親の対応

「友だちのおもちゃを取ってしまった」「自分のおもちゃを取られてしまった」このような「おもちゃトラブル」は、子育て中、多くの方が経験する悩みの1つです。中には、「盗み癖があるのでは」と心配になってしまう方もいるようです。
しかし多くの場合、こういったトラブルには年齢が大きく関係しており、まだやりとりの学びの段階にいるためについ手が出てしまうといった場合がほとんどです。
なぜ「おもちゃトラブル」が起こるのかを年齢別に確認しながら、親が現場でできる対応について、公認心理師の佐藤めぐみさんにアドバイスしていただきます。
なぜ人の物を取るの?年齢別に見る子どもの心理

一般的に、人の物を取るのは「悪いこと」ですが、子どもの場合、「悪意」はなく、「成長の過程」が大きく関係していることが多いものです。ここでは年齢別になぜ人の物を取ってしまうのか、その心理を解説します。
【2〜3歳】
2〜3歳では、「これは誰々の物」といった所有の概念がまだ十分に発達していません。そのため、「欲しい」と感じたものが目の前にあれば、反射的に手を出してしまうのがごく自然な反応です。
公園の砂場で他の子が使っているスコップを取る、などは典型的な例です。お友だちが持っているおもちゃを「いいな」と思ったら、自分の物と同じような感覚で手に取ってしまうのです。この時期は言葉でのコミュニケーションもまだ発達過程にあるので、「貸して」という言葉よりも、「取る」という行動が先に出てしまいがちです。
徐々に社会的に望ましい行動を習得していく時期ですので、「これは〇〇ちゃんの物だよ」「『貸して』って言ってみようか」と所有の概念を意識した声掛けをしていきましょう。
【4〜6歳】
4歳頃になると、「これは友だちのおもちゃ」「勝手に取ってはいけない」といった社会的なルールを理解し始めます。
しかし、頭では「ダメ」とわかっていても、欲求をコントロールする力がまだ未熟なため、「欲しい」という気持ちが勝って手が出てしまうことがよくあります。
よってこの時期は、ルールを教えるだけでなく、自分の気持ちを制御する練習をすることがポイントになります。
【小学生】
小学生になると、ルールの理解に加え、自分の気持ちの抑制もだいぶ身についてきているので、たとえ「いいな」と思ったとしても、勝手に取ったりはしないのが標準的な行動です。
よって、もしこの年齢で人の物を取ってしまう場合は、注意深く対応する必要があります。
特に、何度も繰り返すような場合は、単に「欲しかった」という理由を超えた別の要因が関係している可能性も。ストレスや寂しさ、大人の注意を引きたい気持ちなどの複雑な感情が背景にあることも考えられます。
私の相談室の事例を見ても、親が「盗み癖があるのでは」と心配になるのは小学生辺りが多い印象です。
ただ、この年齢でも一時的に判断力が鈍ることはあります。特に「調子に乗って気持ちが大きくなっている」「いやなことがあって落ち込んでいる」など、気分が平常でないときに、普段なら取らないような行動に出てしまうこともあります。
こういった場合は、単に「取った」という行動だけでなく、子どもの心理状態や周囲の環境にも目を向けることが必要です。
・子どもの成長と善悪の理解度については、こちらの記事もご覧ください。
『【1歳~2歳児】物を投げる・たたく子どもの心理とやめさせる方法』
ケース別「おもちゃトラブル」における親の対応

子どもが「おもちゃトラブル」を起こした時、どのように対応すればよいのでしょうか。ここでは、具体的な事例別に親の適切な関わり方をご紹介します。
【ケース1】友だちの家からおもちゃを持ち帰ってしまった
小学生になり、子どもだけで友だちの家を行き来するようになると、「友だちの家から帰ってきたら、見慣れないおもちゃがバッグに入っていた」というようなことも起こり得ます。
こんな場面に遭遇したら、まずは親が気持ちを落ち着けて状況を確認しましょう。その場で子どもを問い詰めると、ウソをついたり、反抗したりと事を複雑にさせてしまう可能性があるからです。
たとえ故意に持ち帰ったとしても、「〇〇ちゃんのおもちゃ、間違って持って帰って来ちゃったみたいね」のような声掛けで、子どもの良心に働きかけ、正しい行動へと導いていけると望ましいです。
そして、親が同伴して友だちの家へ返しに行き、子どもが自分の言葉で「ごめんね」を伝える機会を設けます。この「返す、謝る」の経験が、「人の物を勝手に持ち帰ってはいけない」という学びにつながります。
【ケース2】自分の物を取られて泣いてしまった
子どもが自分のおもちゃを取られて泣いている場合、まずは、「取られちゃって悲しいね」「いやだったね」と子どもの気持ちをしっかりと受け止めてあげましょう。親に状況を理解してもらえたことで、子どもはひとまず安心感することができます。
ただ、まだおもちゃが手元に戻ってきているわけではないので、年齢的に可能であれば、解決方法を一緒に考えます。
こういう場を活用し、子どもが自分でピンチを解決する練習ができると理想的なので、まずは「どうしたらいいかな?」と問いかけ、子どものアイデアを引き出してみましょう。
いい案が出ないようなら、「『返して』って言ってみようか?」「ママと一緒に言ってみる?」など具体的な対処法を提案し、できれば子ども自身で行動を取れるよう促してみます。
アクションを取っても、相手の子がなかなか返してくれない場合は、親が間に入って「順番で使おうか」などと働きかけることも必要でしょう。また、このタイミングで相手の親御さんにも状況に気づいてもらい、一緒に動くいてもらうというのがとても大切です。
双方の親が上手に介入できると、その場で子どもが学べることも多くなります。
【ケース3】貸したくなくてトラブルになった
友だちに「貸して」と言われても、自分のお気に入りの物だから「貸したくない」という状況もよくあります。この場合は無理に貸させる必要はありません。「自分の物を貸すかどうかは自分で決めていい」と本人の気持ちを尊重してあげることも大切です。
その場合でも、「貸さない」という意思表示をどのように相手の子に伝えればよいのかを教えてあげられるとベストです。
「今は使いたいから、終わったら貸してあげるね」「これは貸せないけど、こっちのおもちゃならいいよ」といった代替案を提示できると望ましいので、年齢に応じ、社会性のある対応を促してあげましょう。
・子ども同士の喧嘩の原因でもよくある「正義感」に関しては、こちらの記事をご覧ください。
『子どもの正義感が強すぎるときの対処法3選』
「盗み癖!?」と不安を感じたとき、見極めたい3つのサイン

ごく稀に起こる「おもちゃトラブル」なら成長の過程として見守れても、中には見過ごせずに「もしかして盗み癖?」と心配になることもあるかもしれません。
そんなときに確認したい子どもの行動は、
1. 繰り返す
2. 嘘をつく
3. 隠す
です。
何度も繰り返し物を取ってしまう、物を取ったことについて嘘をつく、取った物を隠す、これらの行動が見られる場合は、注意が必要です。
単に「物が欲しい気持ち」から取っているのではなく、満たされない思いが隠れているケースもあります。「もっと自分を見てほしい」という寂しさや憤りが発端になっているケースもあります。
人の物を取ってでも自分に関心を向けたいという心理です。その背景に、家庭環境や友だち環境が関係していることもあるでしょう。
もし上記のようなサインが見られる場合、まず大事なのは、親は子どもの絶対的な味方であることを示すことです。その場のショックから、「泥棒みたいなことをして!」「嘘までついて!」と責めると、改善は遠ざかってしまいます。
その行動の背景に何があるのかを探ることが重要ですので、解決が難しいと感じたら、1人で抱え込まずに、園や学校の先生、地域の相談窓口、専門家など、第三者へ相談することも積極的に検討してみてください。
・子どもがウソをついたときの親の対処法に関しては、こちらの記事をご覧ください。
『子どもがウソ、そのときの親の心理とできるウソ対策』
トラブルを”成長のきっかけ”に変える親の関わり方

「おもちゃトラブル」は、親にとっては頭の痛い問題ですが、子どもの社会性を育む貴重な機会でもあります。
人のおもちゃは勝手に取らないのがベスト、でも取ってしまったら、返却し、謝る、という一連の経験を通じて社会のルールを深く学んでもらい、その後の成長につなげましょう。
その1 普段から貸し借りのやりとりを家庭でも
最も望ましいのは、トラブルが起きてから慌てて教えるのではなく、普段から家庭で「貸して」「どうぞ」「ありがとう」「返すね」といったやりとりを自然に行いながら学んでもらうことです。
親子でのやりとりやきょうだい間でのおもちゃの貸し借りなどを通じて、子どもたちは「貸し借り」のルールを学び、円滑なコミュニケーションの基礎を築くことができます。
その2 絵本やロールプレイでモラルを育む
言葉がまだつたない年齢の子どもに社会のルールを教えるのは難しいので、その場合は絵本やロールプレイがおすすめです。
「貸し借り」「友だちと仲良く遊ぶ」をテーマにした絵本を読んだり、人形やぬいぐるみを使って「貸して」「どうぞ」のやりとりを練習したりすることで遊びながら社会性の発達を促すことができます。
その3 親自身も怒るより学びを促す姿勢で
人の物を取るという行為は、親として「許しがたい」と感じやすいため、思わず感情的になってしまいがちです。
しかしこれまで見てきた事例からも、強く叱って改善させようとするよりも、学びを促そうという姿勢で取り組む方が効果的だと感じています。
・落ち着いてから、「どうすればよかったかな?」「次からはどうする?」と一緒に考える
・トラブルの解決後に、「きちんと返せたね」「謝ることができたね」とねぎらう
・「ちゃんとできたとき」に気づいてあげて「『貸して』って言えたね」とほめる
のように、怒ることよりも学びを促す姿勢を心がけるということが望ましいですね。
「人の物を取った」という行動だけに目を向けると、つい不安になってしまいますが、多くの場合、これらのトラブルは成長の過程で起こる自然な現象です。
親が年齢に応じた発達段階を理解し、感情的にならずに適切に対応することで、子どもは社会的に望ましい行動を学んでいくはずです。
必要なときには、周囲に相談したり専門家の力を借りながら、わが子の成長を見守りましょう。
・わが子のほめ方のコツに関しては、こちらの記事をご覧ください。
『 「ほめる」のではなく「認める」ことで子どものやる気はUPする!』

きょうだい喧嘩を親のストレスなく止める方法7選【公認心理師監修】

わが子が他の子に加害されたときの対処法【未就学児編】

相談の場「育児相談室ポジカフェ」&学びの場「ポジ育ラボ」を運営。
専門は0~10歳のお子さんを持つご家庭向けの行動改善プログラム、認知行動療法ベースの育児ストレス支援。ポジ育ラボでは子育てに関する心理学情報を発信するほか、ママ・パパが自分の心のケアを学べるメルマガ講座「ポジ育クラブ」を配信。英・レスター大学大学院修士課程修了。HP:https://megumi-sato.com/